秋の夜空に想いを馳せて―中秋の名月と京都のお月見文化―
西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology.

記録的な猛暑といわれる夏が暦の上では過ぎましたが、厳しい残暑が続きます。
それでも秋の夜長はやってきてくれて、空に浮かぶまんまるな月を見上げて心を落ち着ける…。そんな風情のある「お月見」は、私たちの暮らしに息づいています。
■中秋の名月と芋名月

旧暦8月15日の月は「中秋の名月」と呼ばれ、今年(2025年)は10月6日にあたります。お月見の起源は中国から伝わった「観月の宴」で、平安時代には、貴族たちが宮中で月を愛でながら和歌や音楽を楽しんだといわれています。
やがてこの文化は庶民にも広まり、農作物の収穫に感謝する行事として親しまれるようになりました。お月見にはススキを飾りますが、これは豊作の象徴である稲穂の代わりとして、また月の神様を招くための依り代(よりしろ)とされることからです。
十五夜(中秋の名月)はこの時期に収穫できる芋(里芋)にちなんで別名「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれます。
■十三夜の月、栗名月と豆名月
お月見は十五夜だけではありません。旧暦9月13日の月、「十三夜」も大切にされてきました。
十五夜は豊作を祈願するのに対し、十三夜はすでに収穫された秋の恵みに感謝し、また翌年の豊作を祈る意味が込められています。
今年の「十三夜」は11月2日。「十三夜」はこの時期にちょうど旬を迎える栗や枝豆を供えて「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。
昔から十五夜と十三夜の両方の月を愛でると縁起が良いとされてきましたが、一方で、片方だけしか見ないのは「片見月(かたみづき)」いい、縁起が良くないとされてきました。
秋に二度、十五夜と十三夜の月を楽しむことで、より豊かな季節の恵みに感謝を表す日本独自の美しい風習です。
■月見団子と京都ならではの風習
お月見には、丸い月に見立てた月見団子を供えます。京都では、特に十五夜が「芋名月」と呼ばれるように、団子の形も里芋のように少し細長く作られていて特徴的です。

他にも月やうさぎをモチーフにした和菓子も豊富です。お酒などの飲み物に映る月をいただくことで幸運やツキを呼ぶ「飲月(いんげつ)」も風流です。
■西陣エリアで行われる月にまつわる祭り
十五夜(中秋の名月)の頃には、京都各所で名月を愛でる行事が開催されます。
北野天満宮では、十五夜に「明月祭」が行われ、神前にはずいき芋、里芋、月見団子などが供えられ、月を観賞しながら五穀豊穣を願います。
また、平野神社では「名月祭」、白峯神宮では「観月祭」が催されます。白峯神宮のご祭神である崇徳天皇は、和歌と管弦に秀でた人物で、かつて宮中でも月を愛でながら音楽を楽しんでいたと伝えられています。
静かな夜に浮かぶ月は、昔も今も変わらず、私たちの心を優しく照らしてくれます。
秋の西陣で粋な夜長を楽しんでみてはいかがでしょう。
Special Thanks
Editor
be京都 岡元麻有
Art Gallery be 京都館長。関西学院大学卒業後、広告代理店にて企業の販売促進を手掛ける。京町家で生活しながらbe 京都で文化芸術活動を発信。京都市プロジェクト推進室にしZINE担当。京都市上京区カミングレポーター。
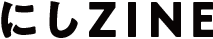



 季節を巡る京菓子
季節を巡る京菓子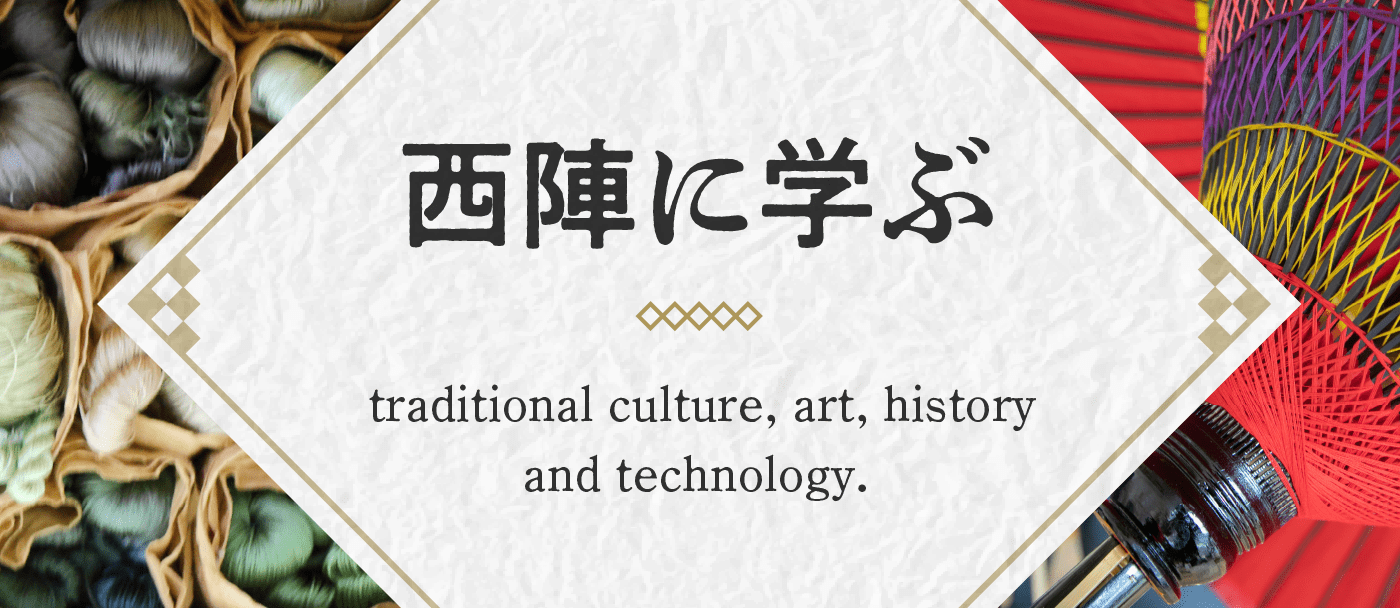 西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology.
西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology.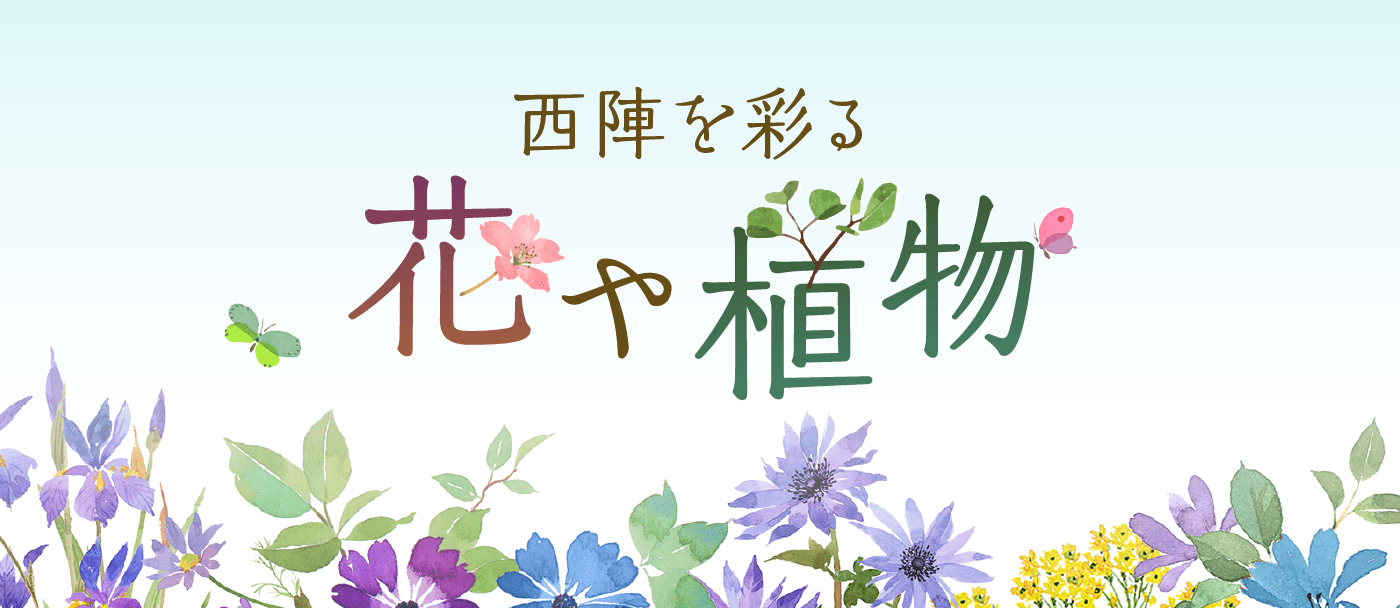 西陣を彩る花や植物
西陣を彩る花や植物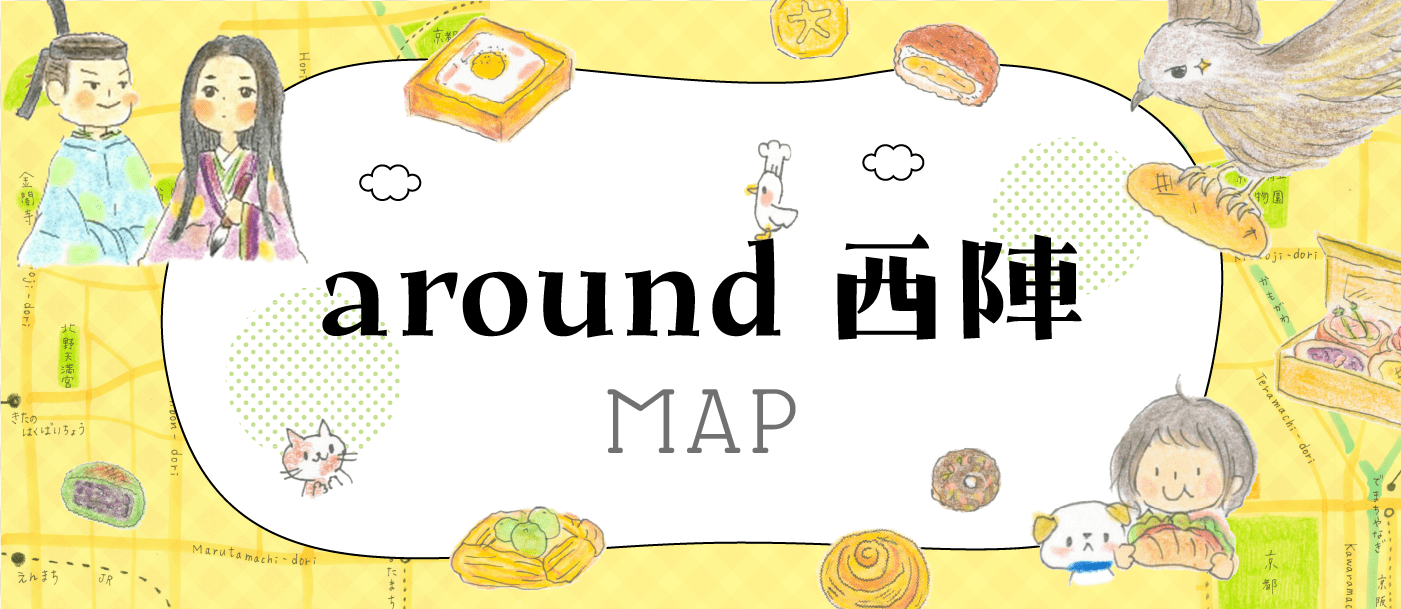 around 西陣 MAP
around 西陣 MAP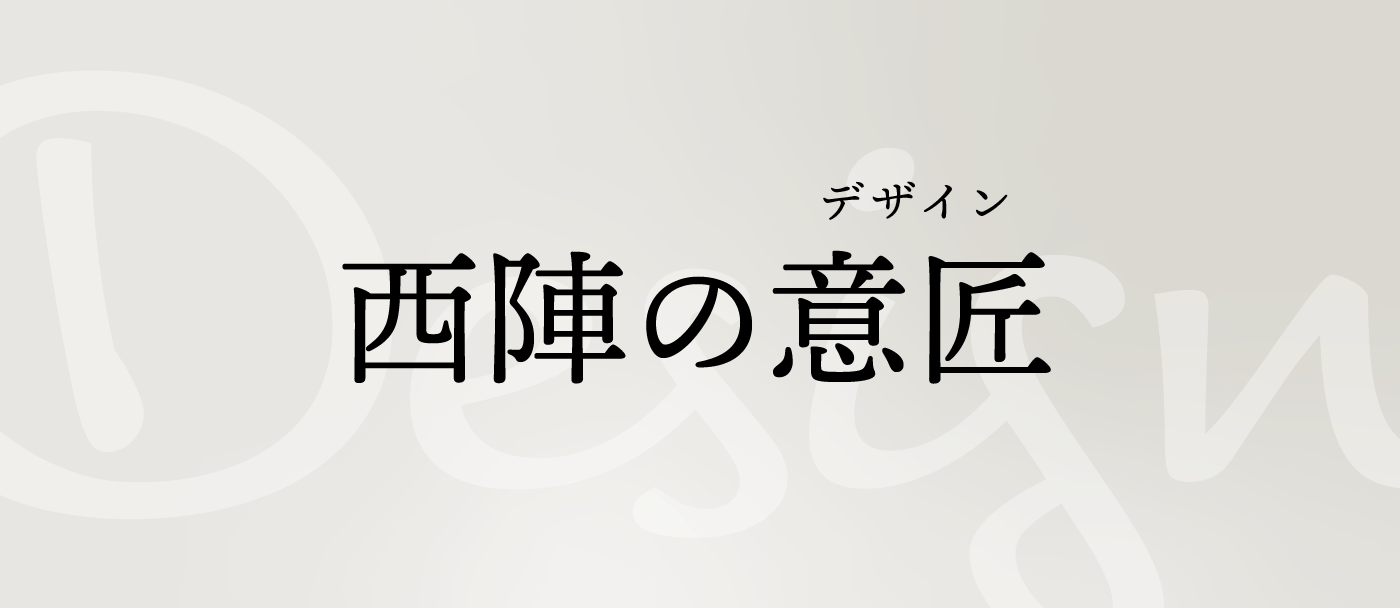 西陣の意匠
西陣の意匠